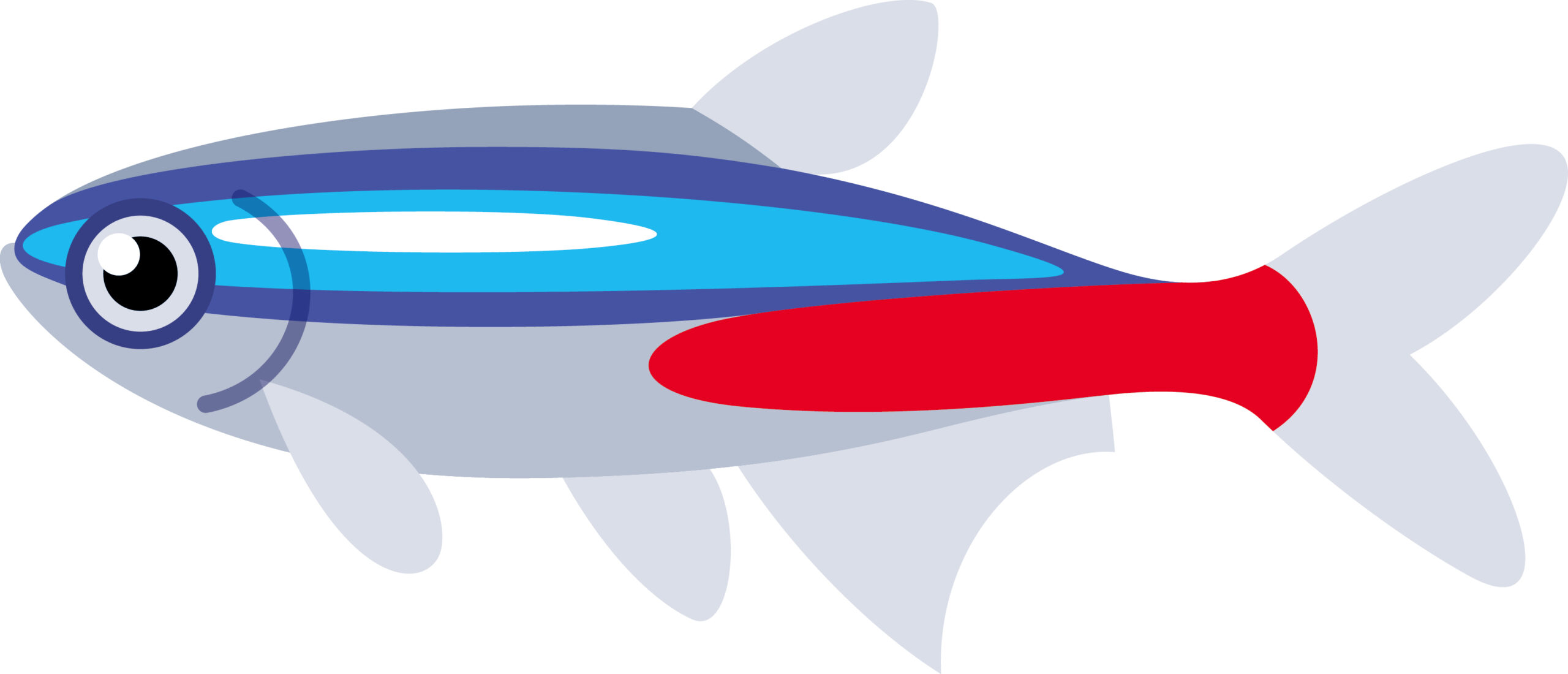カワアナゴの飼育方法を3つのポイントで紹介!
この記事を読んで、初めてこの名前を聞いた方の中には
と驚く方もいるかも知れません。
カワアナゴの背中が黒から白に変わる瞬間。
興奮したりするとすぐ白くなります。 pic.twitter.com/63tWZUU1ig— ナマニラミ(夜採集) (@pN9kCEyiPils1YY) August 1, 2023
カワアナゴは、なかなかペットショップに出回る事の少ない珍しい魚ですが、その姿や行動にはきっと興味をそそられると思います。
ポチップ
カワアナゴの正体&特徴は?
 詳しい分類で見ると、スズキ目ハゼ亜目カワアナゴ科と分類されており、実はハゼに近い仲間である事が分かります。
詳しい分類で見ると、スズキ目ハゼ亜目カワアナゴ科と分類されており、実はハゼに近い仲間である事が分かります。
全長は大きい物で25cm程にもなります。
野生下では河川の下流から河口の汽水域という海水と川の水がぶつかり合っているところに生息し、倒木や岩の影、アシ等の植物の根元に隠れて暮らしています。
中には捨てられた空き缶やビン等を隠れ家として利用する個体もいます。
夜行性で、暗くなると餌となる小魚やエビ、昆虫を捕食しに隠れ家から出てきます。
その口は大きく、小さいながら鋭い牙がたくさん生えた獰猛な見た目をしています。
体色は個体差があり、だいたいは背面の色は明るく、それ以外の部分は暗い色をしています。
体色を変化させて川底に溶け込む事ができます。
カワアナゴの特徴や正体が分かったところで、早速飼育のポイントを紹介していきたいと思います。
ポチップ
飼育のポイント
- 生き餌を確保する事!(人工の餌に餌付かない個体が多いです。)
- 混泳はせず、単独飼育!(肉食なので夜のうちに他の魚を襲ってしまいます。)
- 隠れ家を入れてあげる事!(元々隠れて暮らしている魚です。安心できる場所を与えましょう。)
カワアナゴの飼育方法
水槽、フィルターについて
水槽のサイズですが、カワアナゴの全長と泳ぐスペース等を考慮して60cm以上の水槽が好ましいです。
水温、水質について
15〜25℃の範囲であれば飼育が可能ですが、水温の変化が大きかったり頻繁に変動してしまうと体調を崩してしまうので、ヒーターを入れて温度を一定に保つようにしましょう。
水質は中性〜弱アルカリ性を好みます。
水換え、掃除について
水の汚れ具合によりますが1〜2週間に一回、1/3〜1/2の量の水を換えます。
水道水は必ずカルキ抜きをしてから使ってください。
ガラス面の汚れは水を含ませたスポンジで擦って落とします。
底砂について
金魚や川魚飼育用の砂や砂利であれば問題はありません。
レイアウトの注意点
石や水草を使って隠れ家を作ってあげるのはもちろんの事ですが、力が強い魚なので、何かされても崩れない隠れ家を作りましょう。
給餌(エサ)について
カワアナゴは動くエサに反応するものの、人工飼料にはあまり見向きもしてくれません。
そのため、基本的に生き餌がメインとなります。
メダカやアカヒレも良い餌になりますが、特にエビは好んで食べます。
ポチップ
ある程度の数をまとめて確保しておきましょう。与え方は、照明を落として15〜30分後くらいに食べきれる量を与えます。
意外と盲点、小さなカワアナゴの餌
ポチップ
やっと手に入れたカワアナゴが、3〜5cm程の小さい個体で餌に困る方もいると思います。
そんなサイズにオススメの餌がアカヒレの稚魚です。
まとめ
ネックである生き餌の確保さえできれば、意外と簡単に飼育する事ができます。
また、人に馴れやすい魚なので、よく馴れた個体は昼間でも餌をねだってきます。
カワアナゴの名前の由来は諸説ありますが、顔がアナゴに似ているという説と、その身の味がアナゴに似ているという説もあるようです。
そんな彼らですが、飼育下では丈夫な魚であるものの、野生下では環境悪化等の理由で生息数が減り、保護している地域もあります。意外と複雑な事情を抱えた魚でもあるのです。
ポチップ